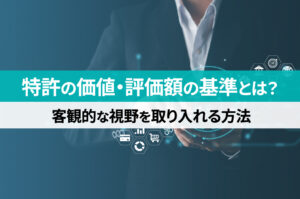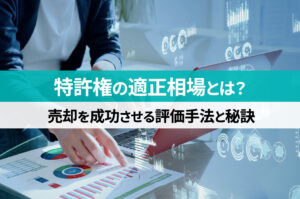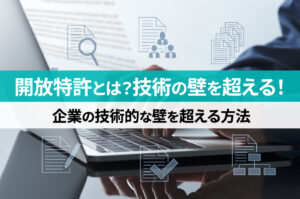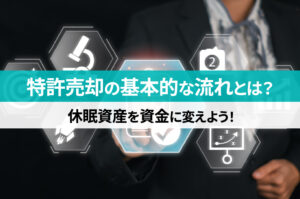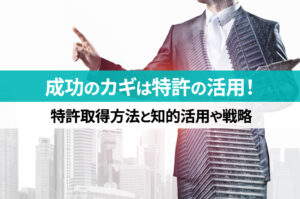特許侵害は登録済みの特許を無断使用する行為であり、新規アイデアを運用するうえでは、特許侵害に該当しない対策が必要です。
登録済みの特許の検索は簡単に行えますが、調べ方を間違えると、特許侵害に気付かないまま事業を進めてしまいます。
この記事では、特許侵害について、事前に調べる方法や発覚した際の対応などをまとめました。
- 特許侵害を事前に調べた場合のトラブル回避や事業の撤退リスク軽減
- 特許侵害にあたる行為や判定基準
- 特許侵害の調べ方と弁護士等の専門家の活用
- 特許侵害発覚後の交渉や法的手続きの対応
- 開放特許を活用した特許侵害の回避
会社や個人事業主として新規アイデアを積極的に採用している場合は、リスク回避の参考にしてください。
特許侵害を事前に調べてトラブル回避や事業の撤退リスクを減らす
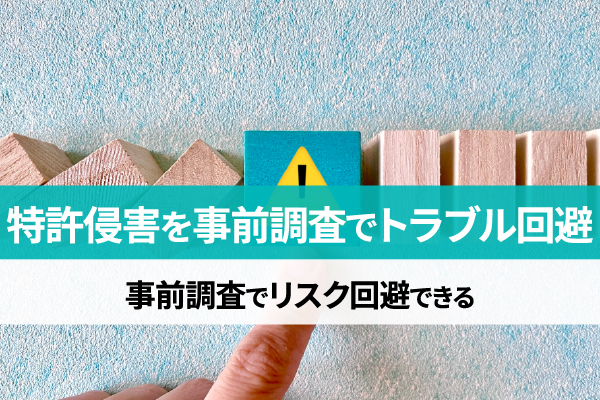
特許侵害は登録済みの特許において、権利者にあたる特許権者の許可を得ずに、無断で商品の販売や技術を利用する行為です。
自身で素晴らしいアイデアを発明したと思っていても、実際はすでに登録済みの特許商品や技術の可能性があります。

特許侵害が発覚した後も冷静に対処すれば問題に発展しませんが、最初から防げるリスクは対策しておいたほうが良いでしょう。
特許権者とトラブルが発生すると、相手側の訴訟による長期的な対応や事業の中止を余儀なくされる可能性があります。
そのため、企業や個人で新規アイデアが出た際は、実際の運用や市場へ投入する前に必ず特許侵害の調査を行ってください。
特許侵害は特許にあたる物や方法が特許権者の許可なく実施されている

特許法の特許権第六十八条において、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有すると明記されています。
より簡単に書くと、特許権者は特許を独占して使えるという意味であり、特許侵害はこの権利を侵害している状態です。
特許法の特許権第百一条の侵害とみなす行為では、特許を以下の3つに分類しています。
- 物:商品やプログラムなど
- 方法:開発技術や修理など
- 物を生産する方法:特定の商品やプログラムを発明する技術など
上記の特許にあたる物や方法について、生産や譲渡、輸入または譲渡の申出をする行為が特許侵害に該当します。
たとえば、特許を持つ電子機器を家電量販店の無断で展示した場合、商品を販売するための展示として特許侵害にあたる可能性があります。
特許侵害は内容が完全に一致する直接侵害を基準にして判断される

特許侵害では、登録済みの特許に記載された項目を構成要件として、特許侵害の疑いがあるアイデアの内容と比較して判断します。
特許侵害を種類として分類すると、以下のとおりです。
- 直接侵害:特許として登録された項目に記載されたすべての構成要件を満たしている
- 間接侵害:構成要件に該当しない場合でも、直接侵害を誘発する可能性が高い行為を実施している
- 均等侵害:すべての構成要件を満たしていないが、実質的には該当する特許と同じ発明をしていると評価される
直接侵害は登録済みの特許と完全に同じ構成要件だった場合に成立するため、少しでも違いがあった場合は成立しません。
しかし、直接侵害に該当する可能性が高い行為や少しの書き換え等で別のアイデアのように見せるものは、間接侵害や均等侵害にあたります。
特許の分類や特許侵害の種類を判別するための架空の例
架空の会社と特許を例にして、新しい特許が取得されるまでの流れは、以下のとおりです。
- A社が特許を持つ技術Xについて、B社がライセンス契約で技術Xを借りる
- B社はA社の技術Xにより新商品Yの開発に成功して、新商品Yの特許を取得する
- B社が新商品Yの開発を進める過程で、A社の技術Xを活かせる装置を開発した結果、新しい装置と技術を用いた製造方法が生まれる
- 両社で協議を行い、新しい製造方法を新技術Zとして、A社とB社が共同で特許の取得を申請する
上記の内容で登場した技術Xや新商品Y、新技術Zを特許における分類に当てはめると、以下のように分けられます。
- A社が特許を持つ技術X:方法
- B社が特許を持つ新商品Y:物
- A社とB社が共同で特許を持つ商品Yを製造するための新技術Z:物を生産する方法
例の中で、B社は正式に特許技術Xを利用するため、A社とライセンス契約を結んでいました。
しかし、仮にライセンス契約を結ばずに特許を使用した場合、以下の特許侵害に該当する可能性があります。
- B社はA社が特許を持つ技術Xを無断使用した:直接侵害
- B社はA社が特許を持つ技術Xに必要な専用部品について、A社の許可を得ずに、無断で販売した:間接侵害
- B社はA社が特許を持つ技術Xについて、動作の順序を少し変えて自社技術として使用した:均等侵害
均等侵害の成否としては、元の特許から簡単に思い付く範囲で動作や部品のみ入れ替えた場合、特許侵害と判断されます。
特許侵害を調べる際は該当する範囲や種類を明らかにする
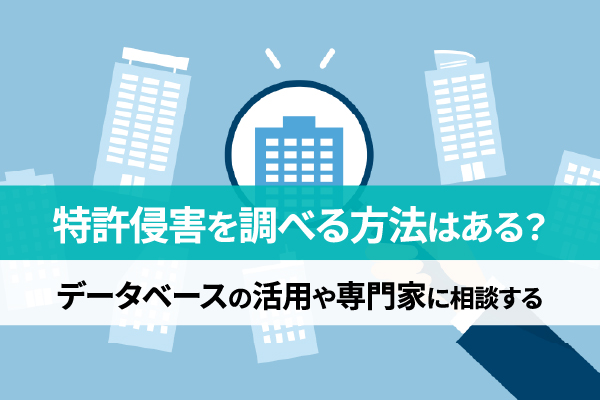
特許侵害の調べ方について、大まかな手順は以下のとおりです。
- 特許侵害に該当する特許、もしくは類似する特許を特許情報プラットフォームから検索する
- 特許の内容を確認して、特許侵害に該当する可能性がある範囲を確定する
- 直接侵害や間接侵害、均等侵害のいずれかに該当するか判断する
- 特許侵害の可否によって、示談交渉などの対応に移る

登録済みの特許を掲載した特許公報は、独立行政法人工業所有権・研修館の特許情報プラットフォームから検索できます。
特許侵害に該当する特許を見つけた後は、記載された内容と自社のアイデアを比較して、本当に特許侵害をしているか判断します。
データベースでは特許番号や関連する単語から検索して見つける
特許侵害の指摘や特許権者からの警告があった場合は、該当する商品や技術について、以下の情報を収集します。
- 特許番号
- 商品名、技術名
- 特許を保有する会社、個人名
特許番号の場合はすぐに発見できますが、商品名や会社名では、ほかの特許に引っかかる可能性があります。
一方、特許侵害について自主的に調査する場合は、該当する可能性のある固有名詞や単語を考えます。
たとえば、にんじんを用いたレトルト食品を製造したい場合、材料以外にも製造時に用いる加工や圧迫する技術なども検索対象です。
特許侵害を調査して該当する範囲や種類を確定させるまでの架空の例
架空の会社と特許を例にして、特許侵害の成否を調べる際の流れは、以下のとおりです。
- D社はワッフルをステンレス板2枚に挟んで焼き上げて、ワッフルサンドを作るアイデアを思い付く
- 特許を調べた結果、パンを鉄板2枚に挟んで焼き上げて、ホットサンドを作るアイデアについて、E社が特許を登録していた
- 登録済みの特許からパンを鉄板2枚に挟んで焼き上げが特許侵害に該当する範囲と確定する
- D社が使用するのはワッフルとステンレス板であるため、直接侵害ではない
- 鉄板に近い素材のステンレス板を使用しており、挟んで焼き上げる点は一致しているため、間接侵害や均等侵害にあたる可能性がある
- 弁護士に相談した結果、特許侵害に該当すると判断される
- 思い付いたアイデアで事業を進めたいため、D社はE社と交渉してライセンス契約を結ぶ
- D社はパンを鉄板2枚に挟んで焼き上げの特許技術を借りて商品開発できる
あくまで架空の例であり、鉄板に挟んで焼くような簡単に思い付く技術は、そもそも特許権の取得が認められません。
しかし、特許侵害の成否を調べるうえでは、上記のような流れで該当範囲や特許侵害の種類を絞っていきます。
特許侵害の範囲や種類については弁護士等の専門家への相談も視野に入れる
特許侵害に該当する特許を見つけた際、直接侵害の場合は内容の完全一致で特許侵害したと判断できます。
しかし、間接侵害や均等侵害の場合は、特許のどの範囲が引っかかっているか、判断がつかない可能性があります。
個人で該当しないと判断して、実際に運用や市場へ投入してから特許侵害だと判明すると、事前に調査した意味がありません。
特許侵害を調べる場合は、最終的な判断をする前に弁護士等の特許に詳しい専門家に相談しましょう。
弁護士等の専門家は過去の判例や経験から、特許侵害の範囲や種類を高い正確性で判断します。
示談交渉や法的手続きへ進む際も弁護士等の専門家を頼れるため、積極的に相談してください。
特許侵害が発覚後は示談交渉から始まって法的解決まで発展する可能性がある
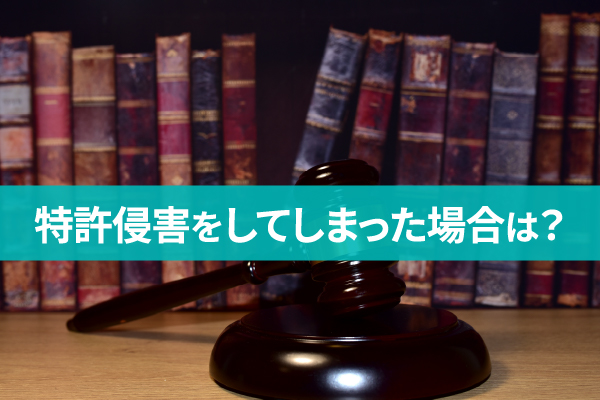
事前に特許侵害について調べた場合でも、調査不足や類似する特許により特許侵害に該当する可能性があります。
特許侵害が発覚してから特許権者と特許侵害の疑いがある者がやり取りする流れは、以下のとおりです。
- 特許権者から警告書が送付され、損害賠償やライセンス契約による示談交渉が持ちかけられる
- 示談交渉が決裂した場合は、特許権者側が訴訟や裁判外紛争処理手続など、法的手続きが進められる
- 訴訟で特許権者側が勝訴した場合、差止請求や損害賠償請求など、法律に基づいた救済を特許侵害した側に求められる
上記は解決が長引いた場合の例であり、最初の示談交渉でお互いに納得した場合は、法的手続きまで進む必要はありません。
一般的には特許権者側も事態を大きくしないために、警告書で示談交渉を求めるところからやり取りが始まります。
特許権者側が事業に理解を示した場合は、ライセンス契約で利用料を継続的に支払う代わりに特許を利用できる可能性もあります。
悪意を持って特許侵害を利用する相手に対しては対抗できる情報を集める
悪意のある特許権者の場合、損害賠償を得るために本来とは異なる内容のアイデアに対して、特許侵害を主張する場合があります。
警告や訴訟された側にも主張する権利があるため、理不尽な特許侵害の主張については対抗しましょう。
示談交渉に応じる場合は、弁護士等に交渉を代理してもらったほうがプロの対応で有利に立ち回れる可能性が高まります。
法的手続きを行う場合は費用がかかるため、示談交渉に弁護士等を介入させた時点で、悪意のある特許権者側が諦める可能性もあります。
万が一、示談交渉が決裂して法的手続きに進む場合は、特許侵害に当てはまらない証拠や情報の収集が必要です。
どのような解決方法になる場合でも、個人で判断や交渉するのは難しいため、基本的には弁護士等の専門家を頼ってください。
ライセンス契約できない場合は均等侵害に当てはまらない範囲で改良する
特許侵害を主張された後でも、特許権者側が許す場合はライセンス契約や譲渡など金銭によるやり取りで特許を使える可能性があります。
しかし、特許権者側が応じない場合は、新しいアイデアを成立させるための商品や技術が使えません。
事業を取りやめるのが難しい場合は、特許侵害で問題になった部分について、代替できるアイデアを考えましょう。
ただし、技術や部品の一部分のみを変えても、均等侵害にあたる可能性があります。
代替アイデアを思いついたときも、特許侵害の調査や弁護士等の意見を聞いてから本格的な運用に移ってください。
特許侵害を防ぐために開放特許によるライセンス契約や譲渡を活用する

特許侵害を防ぐ手段の1つとして、最初からライセンス契約や譲渡を前提にして、別の人が権利を持つ特許を探す方法があります。
特許の中には特許権者が自ら希望して、全体に公開する開放特許があり、データベースサイト等で公開しています。
開放特許の場合は新規アイデアを自社で考える時間やコストを削減できて、正式な利用手続きから特許侵害にも該当しません。
そんな開放特許を探す際におすすめのサイトは、IPマーケットの開放知財データベースです。
開放知財データベースは初心者でも利用できる環境を整えている
IPマーケットの開放知財データベースでは、特許を取り扱った経験がない人でも簡単に使えるように、デザインや機能が工夫されています。
開放特許の検索からライセンス契約や譲渡されるまでの流れは、以下のとおりです。
- キーワード検索や特許番号、ジャンルから、自社に適用できる特許技術や商品を検索する
- 適切な特許が見つかった場合、チャット機能で特許権者に対して内容や条件などを質問する
- 特許について納得した場合は、メールアドレスや電話番号に連絡して、特許権者と交渉する
- 交渉結果から、特許の譲渡やライセンス契約を行う
- 該当特許による技術開発や商品販売が可能になる
データベースの検索は無料で利用できて、特許権者と本格的な交渉に入る前にチャット機能で軽いやり取りも行えます。
開放知財データベースがプランによって機能の利用回数や制限が変わる
IPマーケットの開放知財データベースでは、無料プランを含めた以下の3種類の主要プランがあります。
| プラン | ベーシック | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 月額 | 無料 | 1,280円 | 50,000円 |
| 開放特許データベース検索 | あり | あり | あり |
| AIレコメンド機能 | 月3回まで | 無制限 | 無制限 |
| ソート検索機能 | なし | あり | あり |
| フィルタリング機能 | 一部利用可能 | 無制限 | 無制限 |
| 専門家サポート付きメッセージ機能 | なし | なし | あり |
| 特許査定、活用アドバイス(月1回打ち合わせ) | なし | なし | あり |
※2025年10月時点
上記のプランには追加料金でオプションも付けられるため、希望する機能や利用頻度に合わせてプランとオプションを選びましょう。
特許侵害の可能性を調べてから新しいアイデアを運用していく
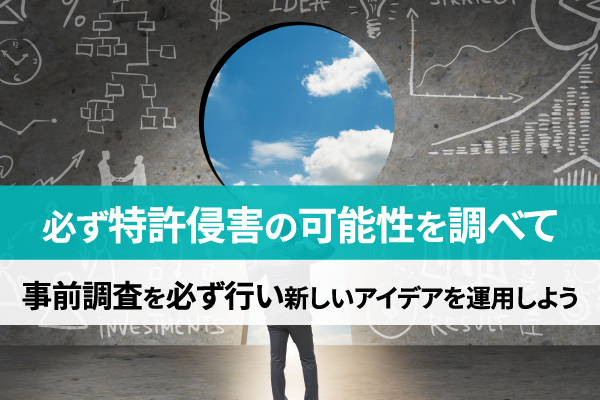
特許侵害について、事前に調べる方法や発覚した際の対応などをまとめると、以下のとおりです。
- 特許が無断で生産や譲渡等で実施された場合は特許侵害に該当する
- 登録済みの特許の構成要件と完全に一致した場合は直接侵害と判定される
- 構成要件と完全一致しない場合も間接侵害や均等侵害に該当する可能性がある
- 登録済みの特許を調べる際は特許番号や関連する固有名詞で検索をかける
- 特許侵害が発覚した場合、最初は特許権者の警告書から示談交渉を行う場合が多い
- 示談交渉で解決しない場合は、訴訟などの法的手続きを行い、成否を争う
- 特許権者の成否判断や示談交渉の代理として弁護士等の専門家を活用する
一方、特許侵害に該当していた場合でも、特許権者との交渉次第でライセンス契約や譲渡により特許を利用できる場合があります。
特許を自分のアイデアから作る点にこだわりがない場合は、開放特許も活用できるため、特許侵害の対策として検討してみてください。