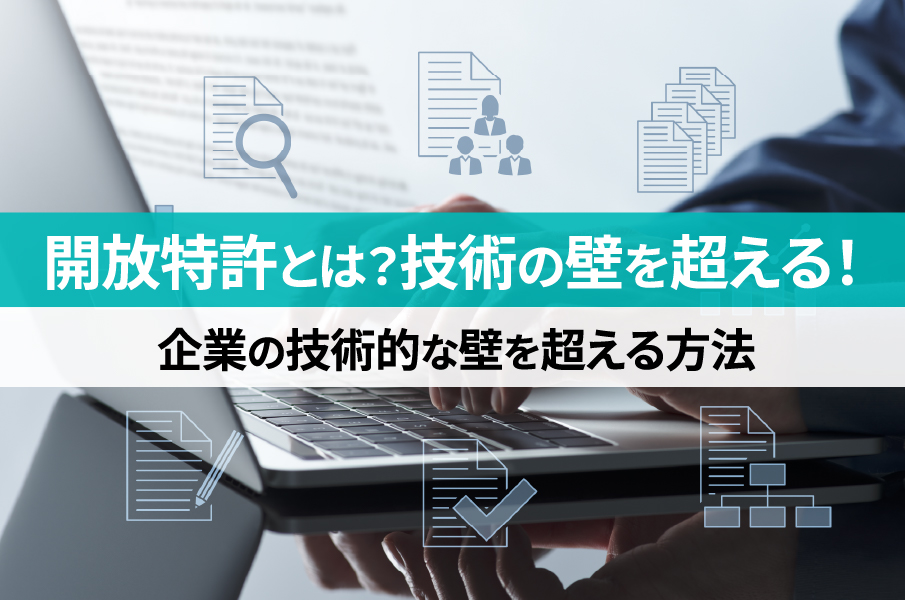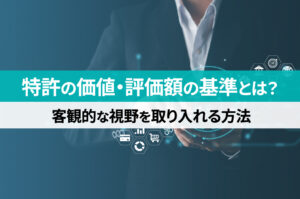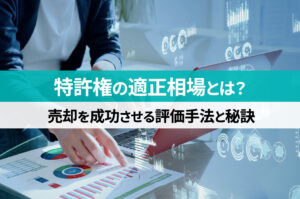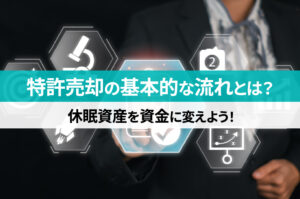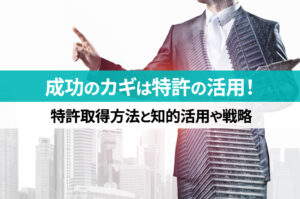中小企業や個人事業主が製品開発を実施すると、技術的な壁に直面するケースは多いはずです。
しかし、本記事で紹介する開放特許を活用すると、中小企業や個人事業主でも製品開発の技術的な壁を打ち破れます。
- 開放特許とは自社の特許権を他社へ開放すること
- 開放特許の利点は開発コストや開発期間を軽減できる
- 注意点はライセンス契約が終了した後の特許権侵害
- 開放特許を見つける方法は開放特許情報データの検索がある
- 知財ビジネスマッチングの参加でも開放特許を見つけられる
この記事では、開放特許について、はじめての人にもわかるように解説しています。
開放特許を活用する利点なども詳しく解説しているため、製品開発に行き詰まっている中小企業や個人事業主はぜひ参考にしてください。
開放特許とは自社の特許権を他社も利用できるように提供すること

開放特許とは、自社が取得している特許権を他社に対して提供することです。
自社の技術力だけでは新製品の開発が難しい場合でも、開放特許の活用によって他社の特許権を取り込むと時間やコストを削減できます。

特許権を開放する側が開放特許の提供者にあたり、特許権を譲り受ける側が利用者になります。
そもそも自社の特許権を提供してまで世間へ技術力を公開している理由は、主にライセンス料によって現金を調達したり、ビジネスチャンスを広げたりするためです。
他にも大手と中小企業によって開放特許を提供している理由は異なるものの、大手企業が特許権を開放すると自社のイメージアップや業界全体の発展などにつながります。
一方で、中小企業が開放特許によって特許権を提供すると、世間への知名度が上がったり大企業と良好な関係性を築けたりなどの利点があります。
| 大企業 | 中小企業 | |
|---|---|---|
| 開放特許の提供者の利点 | ・イメージアップにつながる ・業界全体の発展につながる ・人手が集まる | ・知名度が上がる ・ビジネスチャンスが広がる ・大企業や大学と関係性を築ける ・ライセンス料を得られる |
なかでも開放特許の提供者における利点は、利用者が支払うライセンス料が挙げられ、中小企業にとってはまとまった資金の獲得が可能です。
中小企業が開放特許を提供している理由はライセンス料を獲得できるから
自社の特許権を他社に提供すると、開放特許の利用者からライセンス料を徴収できるため、安定した収益を得られます。
ライセンス料とは、特許権や著作権といった知的財産権を他社に提供した際に支払われる料金のことです。
ライセンス料の支払い方法も双方の同意によって決まり、主に以下のようなものが挙げられます。
| 開放特許におけるライセンス料の支払方法 | 概要 |
|---|---|
| 定額支払 | 月単位や年単位で支払い続ける |
| 一括支払 | 契約時に一括で支払う |
| 一定割合支払 | 売り上げに対して一定割合を支払う |
定額支払は、ライセンス料を月単位や年単位で支払い続ける支払い方法です。
一括支払は、開放特許の契約時に提供者に対して一括で支払います。
一定割合支払は、開放特許によって発生した売り上げに対して、3%〜5%のライセンス料を支払う方法です。
利用者と良好な関係を築けると、人材や新しいアイデアが集まり、さらなる事業発展にもつながります。
開放特許で特許権を提供すると優秀な人材や最先端の技術を集められる

開放特許によって特許権を提供すると他社との交流が増えるため、外部機関を通して優秀な人材や最先端の技術なども集まります。
例えば開放特許によって大学といった外部機関との交流が深まると、最先端の技術に興味を持っているエンジニアを集められたり、優秀な技術者をスカウトできたりします。
さらに、新しい技術やノウハウなども開放特許によって触れる機会が増えるため、新製品を開発するきっかけにもなるかもしれません。
他にも、大手企業が開放特許を実施すると、思わぬビジネスパートナーに遭遇できる可能性があります。
そのため大企業は積極的に開放特許を実施しており、さまざまな企業や業種と交流を図っているのが実情です。
開放特許は自社のイメージアップにもつながり、主に大企業や大学などに利点があります。
開放特許によって新しい技術が世の中に広まると企業のイメージアップにつながる
開放特許によって新しい技術が世の中に広まると、企業のイメージアップにもつながります。
新しい技術によって人々の暮らしが楽になったり問題が解消されたりすると、社会に貢献した企業とみなされるからです。
さらに、発展途上国や貧困国といった地域に貢献する新しい製品を開発すると、世界的にも自社の評価が高くなります。
自社のブランドイメージが向上すると、資金調達がスムーズになるうえ、優秀な人材も確保できるのが利点です。
一方で開放特許の利点は特許権を提供する提供者だけではなく、その技術を活用する利用者にも挙げられます。
開放特許における利用者の利点は資金不足でも新技術を得られる点

ここまで開放特許における提供者の利点を紹介してきましたが、特許権を購入する利用者にとっても様々な利点があります。
例えば、中小企業や個人事業主が開放特許を活用すると以下のような利点があり、新製品の開発や企業価値の向上につながります。

- 資金力がなくても新しい技術を取り込める
- 製品に対して付加価値をつけられる
- コスト削減につながる
- 大企業のブランドを活用できる
- 新しいビジネスチャンスが生まれる
なかでも資金力が乏しい中小企業や個人事業主にとっては、開放特許はコストをかけずに新しい技術の取り込みが可能です。
企業にとって新しい技術をゼロから生み出すには多額の資金が必要ですが、開放特許を活用するとライセンス料のみに抑えられます。
そのため限られた資金で新しい事業や製品開発に着手したい企業は、積極的に活用した方がよいでしょう。
開放特許を活用すると、開発している製品に付加価値を付けられたり、販売先のネットワークが広がったりなどの利点も得られます。
以下で開放特許における利用者側の利点をそれぞれ紹介しているため、自社の成長戦略の参考としてぜひ確認してください。
自社の製品に対して新しい特許権を活かした付加価値を付けられる
開放特許を活用すると、自社の製品に対して新しい付加価値を付けられます。
例えば、家電メーカーが開放特許を活用して省エネ制御技術を導入すると、自社の家電製品に省エネという付加価値を与えられます。
他にも食品メーカーが最先端の冷凍技術に関する開放特許を活用すると、長期保存でもおいしさを維持できるかもしれません。
そのため自社の製品に何らかの付加価値を付けたい場合には、開放特許を活用した方がよいでしょう。
付加価値は、他社との差別化につながったり売り上げアップに貢献できたりします。
開放特許を活用する利点は、新製品を安価で迅速に市場へ投入できる点も挙げられます。
開放特許を活用すると開発コストの削減や開発期間の短縮につながる

開放特許を活用すると、新製品の開発コストを削減できたり開発期間を短縮できたりします。
新しい製品を開発するにはコストや期間がかかるものの、開放特許を活用するとすでに完成された技術を流用できるため、ゼロから開発を進めなくていいからです。
開放特許に登録されている特許権は、コストや時間を要して生み出されているケースが多く、その技術を簡単に自社の製品に導入できるのが利点になります。
そのため新しい製品を安価で短期間に開発したい企業は、コストや期間を短縮できる開放特許を活用するのが最適です。
開放特許を活用すると、販路の拡大や新たな取引先との出会いも期待できます。
新しいビジネスチャンスが生まれて販売先のネットワークを増やせる
ビジネスチャンスになかなか恵まれない企業でも、開放特許を活用すると販売先のネットワークを拡大できる可能性があります。
開放特許を通じて新しい技術を導入した後は、その提供者の企業と交流を取る機会が多くなり、新たな取引や連携の機会が広がるからです。
さらに提供者企業の取引先や関係機関など様々な団体とつながると、今まで接点がなかった業界や市場への介入も可能になります。
他にも協業パートナーや共同開発の構築にもつながり、新しい技術革新を目指している企業にも役立ちます。
そのためビジネスチャンスに恵まれない中小企業や個人事業主は、積極的に開放特許を活用しましょう。
開放特許はオープンイノベーションのなかでも主流になるビジネス戦略
オープンイノベーションとは、自社だけではなく他社の技術やノウハウを取り入れて、新しい製品およびサービスを生み出すビジネスモデルのことです。
自社の技術力やノウハウだけでは新しい商品開発が難しい場合でも、オープンイノベーションを積極的に導入すると革新的な製品を創出できます。
つまりオープンイノベーションの手法のひとつに、今回紹介している開放特許があるということです。
以下で開放特許とオープンイノベーションの違いを比較しているため、それぞれの違いがわからない場合は参考にしてください。
| 開放特許 | オープンイノベーション | |
|---|---|---|
| 概念 | 特許権を公開する制度 | ビジネスモデルまたはビジネス戦略 |
| 特許権の有無 | あり | なし |
| 範囲 | 特許権に限定 | ・アイデアの募集・共同開発・資本提携など |
オープンイノベーションはビジネスモデルやビジネス戦略であり、特許権が発生しないケースも散見されます。
一方で、開放特許はオープンイノベーションの手法のひとつになり、特許権を公開する制度を指します。
そのためオープンイノベーションを目指す企業は、開放特許を活用した技術連携や新規事業開発を検討するのが効果的です。
ただし開放特許を活用する際はいくつか注意点があり、主に特許権の侵害や適正なライセンス料金などが挙げられます。
開放特許の注意点は特許権の侵害によって刑事罰に科される点
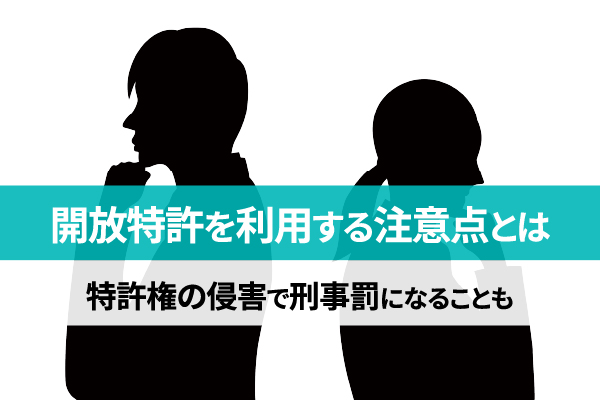
開放特許の注意点はいくつかあるものの、主に特許権侵害が挙げられます。
利用者の場合は、開放特許の契約期間が終了したあとの特許権侵害です。
契約期間が決まっている開放特許は、期限を迎えると譲り受けた特許権を利用できないため、誤って使用すると特許権侵害になります。
一方で、特許権を提供した提供者は、特許権を提供したあとの特許権侵害が挙げられます。
特許権を提供したにも関わらず、自社の製品に提供した技術やノウハウなどが含まれていると特許権侵害につながりかねません。
| 立場 | 注意点 |
|---|---|
| 利用者 | 利用期間経過後の特許権侵害 |
| 提供者 | 提供後の特許権侵害 |
特許権侵害に抵触すると刑事罰に問われる可能性があり、特許法によって1億円以下または3億円以下の罰金を科せられます。
第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
引用元:特許法-e-GOV法令検索
そのため開放特許を実施したあとは、提供者も利用者も特許権侵害に抵触しないよう配慮が必要です。
双方が契約内容や利用範囲を正確に把握して、特許権侵害を防ぐ体制を整えておきましょう。
開放特許の注意点は他にもあり、なかでも利用者側は自社製品への付加価値や他社との差別化の見通しを立てられるかが重要です。
開放特許を利用しても付加価値や差別化できなければ効果を得られない
開放特許によって新しい技術やノウハウを導入しても、自社の製品に付加価値を加えられないと、期待している効果を得られない可能性があります。
開放特許は他の企業も活用しているケースがあり、付加価値がないと自社の独自性や他社との差別化を図れないからです。
そのため開放特許を活用したい企業は、自社の製品に付加価値を加えられるか入念に検討しておく必要があります。
他にも長期的なビジネス戦略を検討しておく方がよく、開放特許を活用したからといってすぐに売り上げにつながるわけではありません。
開放特許を活用する際は、長期的な視野を持って特許権の購入を検討しましょう。
他にも開放特許を実施する際は、ライセンス料金が適正かどうかを専門家に確認してもらう必要があります。
ライセンス契約をする際は専門家ににライセン料金を確認してもらう
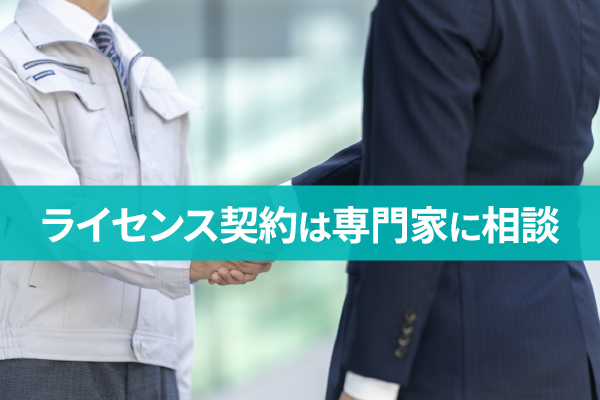
開放特許を活用する場合は、特許権を使用するためのライセンス料を知的財産コーディネーターといった専門家に確認してもらう方がよいでしょう。
知的財産コーディネーターとは、特許や商標など知的財産の活用を促進する専門家のことです。
一般的な適正価格は発生した売り上げの3%〜5%程度ですが、より専門性の高い特許権になると10%以上になるケースもあります。
市場規模や需要性によってライセンス料が高くなるため、開放特許を活用する際は知的財産コーディネーターに適正価格を算出してもらうのが賢明です。
開放特許を実施する際に知的財産コーディネーターに介入してもらうと、契約内容で不備があってもすぐに対応してもらえます。
他にも知的財産コーディネーターは開放特許を見つける支援もしてくれるため、特許技術が見つからない場合にも相談するのが最適です。
一方で自分で開放特許を見つけたい場合は、開放特許情報データからオンラインによって検索しましょう。
開放特許を見つけるにはINPITの開放特許情報データから検索可能
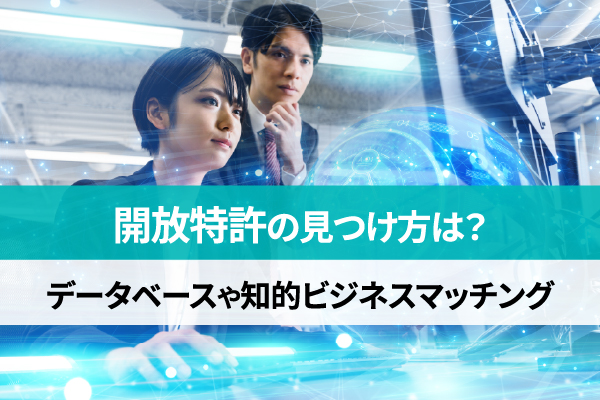
公開されている開放特許を見つけるには、INPITの公式サイトにある開放特許情報データベースから検索が可能です。
INPITとは独立行政法人の工業所有権情報・研修館のことであり、特許庁の所管のもとで運営しています。
主な業務としては、特許情報の提供や知的財産の研修および支援などです。
- 特許情報の提供
- 知的財産に関する研修や教育
- 知的財産の相談および支援など
実際に開放特許情報データベースで検索するには、知りたい開放情報のキーワードを入力します。
例えば、粘着テープに関する開放特許を検索したい場合は、粘着テープまたはテープといったキーワードを入力するだけです。
検索結果は一覧で表示され、目的や技術概要といった情報を確認できます。
さらに、ひとつひとつの開放情報も、以下のような詳細表示によってより詳しく確認できます。
| 詳細表示の項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | ・出願番号 ・出願日 ・出願人 ・公開番号 ・公開日 ・登録番号 ・特許権者 ・発明の名称 ・技術分野 ・機能 ・適用製品 ・目的 ・効果 ・技術概要 ・実施実績の有無 ・許諾実績の有無 ・特許権提供の可否 ・特許権実施許諾の可否 |
| 登録者情報 | ・登録者名称 ・登録者区分 ・問い合わせ先 |
| その他の情報 | ・国際特許分類 ・関連特許の有無 |
基本情報には開放特許の目的や効果および技術の概要などが記載されており、閲覧するだけでも製品開発のきっかけや手がかりを見つけられるかもしれません。
登録者情報は開放特許を登録した企業の問い合わせ先が記載されているため、気になる特許情報が見つかったら直接連絡してみてください。
開放特許情報データベースによる検索方法は、他にも詳細条件検索や国際特許分類検索などもあり、検索機能をうまく使い分けるのが大切です。
検索機能の詳しい解説は簡易操作マニュアルに詳しく記載されているため、開放特許情報データベースを活用する際は一読しておいた方がいいでしょう。
一方で、開放特許を見つける方法は開放特許情報データベースだけではなく、知財ビジネスマッチングといった方法も挙げられます。
知財ビジネスマッチングでも開放特許を提供している企業と接触できる
知財ビジネスマッチングに参加すると、開放特許を提供しているさまざま企業や団体と接触を図れます。
主催者は都道府県の産業振興機関や経済産業局および商工会議所などがあり、他にも知財ビジネスマッチングを専門にしている民間企業も存在します。
実際に知財ビジネスマッチングへ参加するには、産業振興機関や経済産業局の公式サイトにアクセスして、申し込むのが一般的です。
知財ビジネスマッチングによって自社に適した開放特許と出会ったあとは、以下のような流れで商品化を目指します。

開放特許の提供者と順調に話し合いが進むと、ライセンス契約を締結したのちに製品開発に着手できます。
そのため開放特許情報データベースで気になる開放特許が見つからない場合は、知財ビジネスマッチングの参加を検討しましょう。
開放特許の活用によって新商品を開発できた4つの成功事例を紹介

開放特許の活用によって、新しい製品やサービスを開発した企業は多岐にわたります。
以下で開放特許の成功事例を4社に絞って記載しているため、気になる企業があったら公式サイトなどを確認してみてください。
| 企業名 | 業種 | 開発した商品 | |
|---|---|---|---|
| 三島食品株式会社 | 食品 | 凍結含浸技術 | 介護食 |
| 株式会社アイテック | 電子機器 | 粒子材料製造技術 | プロジェクター用スクリーン |
| 株式会社八幡ねじ | 製造 | 車載電力制御ユニットの金属ケースへの制御基板の締結構造 | 基板取付ねじ |
| 佐々木工業株式会社 | 製造 | 真空吸着技術 | 真空吸着ツールスタンド |
例えば食品メーカーの三島食品は介護食にビジネスチャンスを見出そうと、2006年に開放特許によってライセンス契約を締結しています。
活用した開放特許は、凍結含浸技術という広島県が所有している食材を柔らかくする特許権です。
食材の形状をそのままに柔軟化できる製造方法を開発し、今ではりらくという自社の既存製品を柔らかくした介護食を販売しています。
- 2005年3月 りらくやわらか惣菜シリーズ製品化
- 2006年3月 広島県と凍結含浸技術のライセンス契約締結
- 2006年9月 りらくやわらか惣菜シリーズの改良に成功
- 2009年11月 軟質植物質食品の特許権取得
開発期間もわずか半年と早く、2009年には新たな特許権も取得しており、介護施設や病院といった様々な場所で利用されています。
他にも電子機器メーカが開放特許の活用によって新商品を創出しており、今では様々なメディアに紹介されている状況です。
株式会社アイテックは独自のプロジェクター用スクリーンの商品化に成功
株式会社アイテックは超臨海技術を用いた試験装置やプラントなどを製造していましたが、開放特許の活用によって独自のプロジェクター用スクリーンを開発しています。
製品名はパルミルスクリーンといい、窓ガラスなどの透明体に貼るだけでプロジェクターの映像投影が可能になるため、他社製品との差別化に成功しています。
- 2015年7月 ライセンス契約締結
- 2016年12月 スクリーン開発開始
- 2017年9月 スクリーン試験販売
- 2018年3月 パルミルで商標登録
- 2018年4月 正式販売開始
今では大手百貨店やゼネコンなどから発注があり、さらに今後は海外進出も視野に販路の拡充を検討しているようです。
一方で同じ製造業の分野では、工業用のねじを開発している企業が開放特許によって成功している事例があります。
株式会社八幡ねじは基板取付ねじの開発によって他社との差別化に成功
株式会社八幡ねじは、ねじによる敵結部品の開発と製造に取り組んでいましたが、他社との差別化を図るために開放特許を活用しています。
活用した開放特許はトヨタ自動車が保有している、車載電力制御ユニットの金属ケースへの制御基板の締結構造です。
主に制御基板の振動を防止できたり負荷を一定に保ったりできる特許権になり、八幡ねじはその技術を開放特許によってトヨタ自動車とライセンス契約を締結しています。
- 2023年4月 ライセンス契約
- 2023年6月 基板取付ねじの製品名で販売開始
ライセンス契約を締結してから2ヶ月後には、基盤取付ねじという製品開発に成功しており、他社のねじにはない新しい付加価値を創出できているようです。
他にも川崎市にある金属加工会社が、開放特許の活用によって他社との差別化に成功しています。
佐々木工機株式会社は知財マッチングビジネスで新製品の開発に成功
佐々木工機株式会社も開放特許によって成功しており、今では看板商品として真空吸着ツールスタンドを販売しています。
真空吸着ツールスタンドは、工業用の測定器を取り付けるスタンドになり、真空による吸着力によってスタンドと土台を固定しているのが特徴です。
従来のツールスタンドはマグネット方式のため、スタンドを固定するには鉄製品に限られていましたが、真空吸着ツールスタンドはその問題を解消しています。
真空吸着ツールスタンドの販売までに至る期間は、知財マッチングビジネスに参加してからわずか1年9ヶ月と早く、コストと時間を削減できている様子がうかがえます。
- 2013年12月 川崎市知的財産交流会に参加
- 2014年6月 (株)ミツトヨとライセンス契約
- 2015年3月 真空吸着ツールスタンド完成
- 2015年3月 川崎市長会見にて新製品紹介
- 2015年8月 真空吸着ツールスタンド販売開始
製品販売後も川崎市長の会見によって新聞等で取り上げられており、開放特許によって自社の知名度も上がっている状況です。
以上のように開放特許の事例をいくつか紹介してきましたが、いずれの企業も短期間で新製品の開発に成功しています。
そのため製品開発に行き詰まっている企業は、開放特許を活用して、これまでにない新たな製品やサービスを創出しましょう。
開放特許の知識を活かし事業を次のステージへ進めましょう
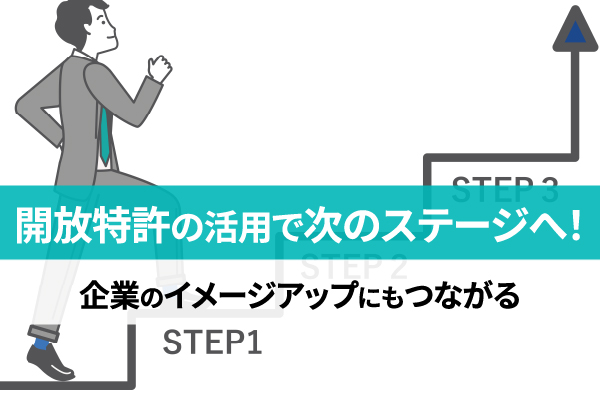
製品開発に行き詰まっている中小企業や個人事業主は、開放特許の知識を活かして事業を次のステージへ進めましょう。
さらに自社の製品に対して付加価値を創出できたり、新しいビジネスチャンスが生まれたりします。
一方で特許権を提供する企業にも利点があり、開放特許を積極的に実施すると自社のイメージアップにつながるかもしれません。
開放特許を見つけるには、開放特許情報データベースを活用します。
開放特許情報データベースを使用する際は、キーワード検索するのが賢い方法です。
他にも知財ビジネスマッチングへ参加すると、開放特許を保有している大企業と接触できます。
開放特許の成功事例は、特許庁や工業所有権情報・研修館の公式サイトなどに掲載されているため、自社の事業と照らし合わせて確認してみてください。